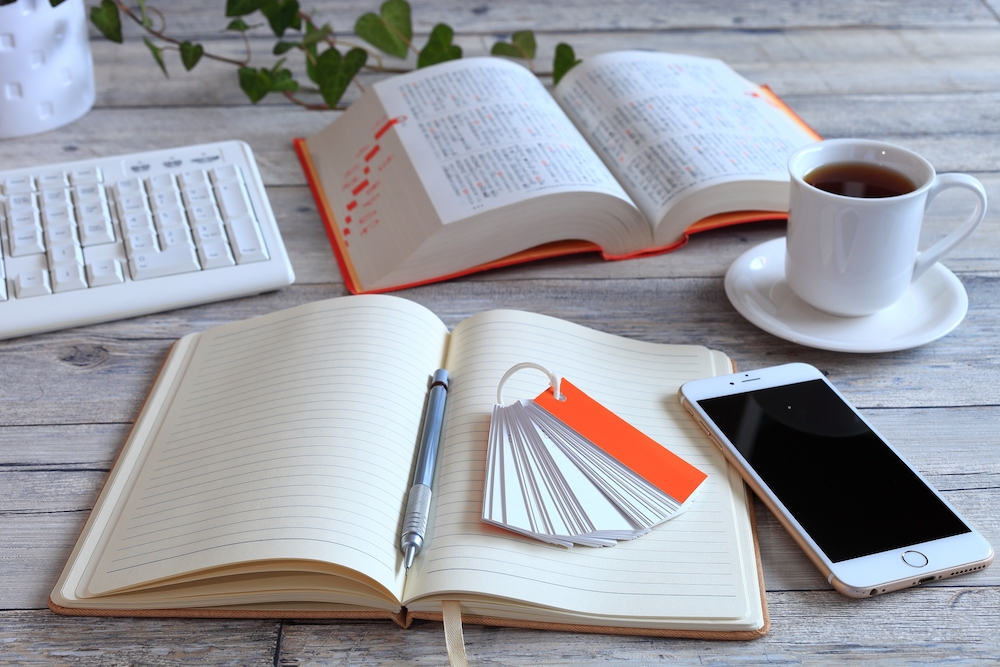あのゴルフ場に通う理由:常連が語る“第二のふるさと”
ふと、ある場所に何度も足を運んでしまうのはなぜだろうか。
初めて訪れたはずなのに、どこか懐かしさを覚える風景。
あるいは、通い慣れた場所だからこその安心感と、そこに集う人々との穏やかな時間。
「あのゴルフ場」に通い続ける常連プレーヤーたちは、口を揃えて言うことがある。
それは、単にゴルフをプレーする場所というだけでなく、まるで心のふるさとのような存在なのだと。
そこには、自身のゴルフの歴史が刻まれ、かけがえのない人々との出会いがあり、そして何よりも、変わらぬ自然と対峙する静かな喜びがあるという。
本稿では、私、佐々木徹が長年見つめてきた「ゴルフコースを巡る紀行」の視点から、常連たちが愛してやまないゴルフ場の魅力に迫りたい。
そこは、ただの芝生が広がる運動場ではない。
風景と記憶が幾重にも重なり合い、訪れる者の人生にそっと寄り添う、特別な場所なのである。
記憶に残る初訪問
出会いの舞台:ニセコのフェアウェイ
私がゴルフコースというものに、特別な感情を抱くようになったきっかけは、北海道のニセコにあるゴルフ場での体験だった。
当時、旅行雑誌の編集者として全国を飛び回っていた私は、取材の一環で偶然その地を訪れたのだ。
羊蹄山が雄大にそびえ、白樺の木々が風にそよぐ。
そんな北国の澄んだ空気の中で、初めて本格的なゴルフコースを歩いた。
それは、単にボールを追いかけるスポーツという以上の、何か深い感動を伴う体験だった。
手入れの行き届いたフェアウェイの緑の絨毯。
戦略的に配置されたバンカーや池の美しい造形。
そして何よりも、そのコース全体が周囲の自然と見事に調和している様に、私は心を奪われた。
ニセコのゴルフ場が教えてくれたこと
- 圧倒的な自然との一体感
- 四季折々に変化するコースの表情
- 計算され尽くしたレイアウトの妙
- プレーヤーの挑戦意欲をかき立てる戦略性
このニセコでの出会いがなければ、私は今も単なる一編集者のままだったかもしれない。
美しさに宿る哲学:造園と土地の歴史
フェアウェイをただ歩いているだけで、なぜこれほどまでに心が満たされるのか。
その疑問は、やがてゴルフコースの設計という分野への興味へと私を導いた。
コースの設計には、造園家の確固たる哲学が息づいていることを知った。
例えば、日本では井上誠一氏や上田治氏といった名匠たちが、その土地の地形を巧みに活かし、自然と調和した戦略性の高いコースを数多く生み出してきた。
彼らは、単に美しいだけのコースを造るのではない。
その土地が持つ歴史や文化、植生までも考慮し、まるで一つの芸術作品を創り上げるようにコースをデザインする。
バンカーの形状一つ、マウンドの起伏一つにも、設計家の意図が隠されている。
それを読み解きながらプレーすることの奥深さに、私はますますのめり込んでいった。
一人の編集者から“歩く紀行作家”へ
ニセコでの感動と、ゴルフコース設計への知的好奇心。
この二つが私の中で結びついたとき、新たな道が開けた。
それは、ゴルフコースを「歩く」ことで見えてくる風景、歴史、そしてそこに集う人々の物語を記録する、「ゴルフコース紀行作家」としての道だった。
以来、私は国内外の数多くのゴルフ場を訪ね歩いてきた。
その土地の風を感じ、設計家の声に耳を澄まし、プレーヤーたちの息遣いに触れる。
そうして紡ぎ出された言葉が、少しでも読者の皆さまを、そのコースへと誘うことができれば、これに勝る喜びはない。
通い続ける理由:ゴルフ場がくれるもの
なぜ、特定のゴルフ場に何度も足を運びたくなるのだろうか。
そこには、プレーヤーの心を捉えて離さない、いくつもの理由が存在する。
変わらぬ風景、変わりゆく自分
ゴルフ場は、いつ訪れても変わらぬ姿で私たちを迎えてくれる。
クラブハウスの佇まい、練習場の雰囲気、そして何よりも、目の前に広がるフェアウェイの風景。
その普遍性が、日常の喧騒から離れ、心をリセットさせてくれる。
しかし、その変わらぬ風景の中で、プレーヤー自身は常に変化し、成長していく。
以前は難攻不落に思えたホールが、経験と技術の向上によって攻略できるようになる。
あるいは、年齢を重ねることで、若い頃とは異なる視点でコースと向き合えるようになる。
変わらぬ風景と、変わりゆく自分。
その対比の中に、ゴルフの尽きない魅力があるのかもしれない。
コースの設計思想に触れる楽しみ
前述の通り、優れたゴルフコースには設計家の明確な思想が反映されている。
通い慣れたコースであればあるほど、その設計の妙を深く味わうことができる。
設計思想に触れるポイント
- 1. ハザードの配置の意図を考える:
なぜこの場所にバンカーがあるのか、池がどのように効いているのか。 - 2. フェアウェイのアンジュレーションを読む:
平坦に見えても微妙な傾斜があり、それがボールの行方を左右する。 - 3. グリーンの形状と速さを把握する:
受けグリーンなのか、砲台グリーンなのか。芝目や傾斜はどうか。 - 4. 風向きや天候による変化を考慮する:
同じホールでも、条件によって全く異なる顔を見せる。
こうした設計家の「問いかけ」に対して、プレーヤーが自身の戦略で「答え」を出す。
その知的なゲームこそが、ゴルフの醍醐味の一つと言えるだろう。
常連たちとの交流と“空気感”
特定のゴルフ場に通い続ける大きな理由の一つに、そこで育まれるコミュニティの存在がある。
顔なじみのメンバーやスタッフ、キャディとの何気ない会話。
共通の趣味を持つ仲間たちと、時に競い合い、時に称え合う心地よい時間。
こうした人間関係が醸し出す独特の「空気感」は、そのゴルフ場ならではの貴重な財産だ。
それは、一朝一夕に出来上がるものではなく、長い年月をかけて少しずつ熟成されていくもの。
新しいゴルフ場にはない、歴史と伝統に裏打ちされた温かみが、そこにはある。
多くの常連プレーヤーにとって、この「空気感」こそが、他の何にも代えがたい魅力となっているのだ。
例えば、歴史あるコースとして知られるオリムピックナショナルの口コミなどからは、長年愛される理由やメンバー同士の温かな交流の様子が伝わってくることもある。
そうした場所ごとの特色を事前に調べてみるのも、新たなホームコースを見つけるための一つの楽しみと言えるだろう。
「第二のふるさと」としてのゴルフ場
ゴルフ場が、単なるスポーツ施設を超えて「第二のふるさと」と呼べるような存在になるのは、どのような時だろうか。
それは、日常の延長線上にありながら、どこか特別な時間が流れる場所となった時かもしれない。
クラブハウスの朝:習慣と安心感
ゴルフ場の朝は早い。
まだ夜の気配が残る中、クラブハウスにはぽつりぽつりと灯りがともり始める。
常連たちは、まるで自分の家に帰ってきたかのように、慣れた足取りでロッカーへ向かい、レストランでコーヒーを嗜む。
その日の天候について語り合ったり、新聞に目を通したり。
あるいは、ただ静かに窓の外の景色を眺めたり。
そこには、長年培われてきた習慣と、それによってもたらされる深い安心感がある。
クラブハウスの喧騒も、仲間うちの談笑も、すべてが心地よいBGMのように感じられるのだ。
クラブハウスでの朝の過ごし方(一例)
| 時間 | 行動 | 目的・感情 |
|---|---|---|
| 到着時 | スタッフと挨拶 | いつもの顔ぶれに安心する |
| ロッカー | プレーの準備、身支度 | 心を整える |
| レストラン | コーヒー、軽い朝食、談笑 | リラックス、情報交換 |
| 練習場 | ウォームアップ | その日の調子を確認する |
| スタート前 | 仲間との合流、談笑 | 期待感を高める |
こうした一つ一つの積み重ねが、ゴルフ場を特別な場所に変えていく。
キャディとの会話に見える日常
ゴルフプレーにおいて、キャディの存在は非常に大きい。
特に、長年そのコースで働くベテランキャディは、コースの隅々まで知り尽くした頼れるアドバイザーだ。
しかし、常連にとってのキャディは、それ以上の存在かもしれない。
「今日は風が右からだから、少し左を狙った方がいいですよ」
「最近、あのバンカーの砂が少し硬くなったみたいです」
そんなプレーに関する的確なアドバイスはもちろんのこと、時には家族の話や近所の話題など、日常のささやかな会話を交わすこともある。
それは、まるで気心の知れた友人のような、あるいは遠い親戚のような温かい関係性だ。
キャディとの会話の中に、そのゴルフ場が持つ日常の顔が垣間見える。
ゴルフを通じた時間の重なりと人生
一つのゴルフ場に長年通い続けるということは、その場所に自身の人生の時間を重ねていくことでもある。
初めて100を切った日。
ホールインワンを達成した瞬間。
大切な友人と最後にプレーした思い出。
子供や孫と一緒にラウンドした喜び。
良い時も、そうでない時も、ゴルフ場は静かにそれら全てを受け止めてくれる。
フェアウェイの木々は、まるで年輪を刻むように、プレーヤーたちの記憶を見守っているかのようだ。
ふとした瞬間に、過去の出来事が鮮明に蘇り、自分の歩んできた道のりを愛おしく感じさせてくれる。
これこそが、ゴルフ場が「第二のふるさと」となり得る、最も大きな理由ではないだろうか。
高齢者とゴルフ場のこれから
私自身も60代を迎え、ゴルフとの付き合い方も少しずつ変化してきたように感じる。
そしてそれは、多くの同年代のゴルファーにとっても同様であろう。
ここでは、高齢者にとってのゴルフ場の在り方、そしてその未来について考えてみたい。
年齢とともに変化するプレースタイル
若い頃のように力任せにボールを飛ばすことは難しくなっても、ゴルフの楽しみが失われるわけではない。
むしろ、年齢を重ねることで、新たなゴルフの魅力に気づかされることも多い。
高齢者のプレースタイルの工夫点
- 飛距離よりも方向性・戦略性を重視:
無理に飛距離を求めず、正確なショットでコースを攻略する知的な楽しみ。 - ギアの選択:
軽量クラブや高弾道で楽にボールが上がるユーティリティなど、体に負担の少ないギアを活用する。 - 健康維持としてのゴルフ:
スコアだけでなく、自然の中を歩くこと、仲間と語らうこと自体を目的とする。 - ショートゲームの重要性:
アプローチやパターといった、熟練の技が活きる分野に磨きをかける。
大切なのは、今の自分に合ったスタイルで、無理なくゴルフを続けることだ。
安全性・利便性への期待と課題
高齢者が安心してゴルフを楽しむためには、ゴルフ場側の配慮も不可欠となる。
ハード面、ソフト面の両方からのサポートが求められる。
高齢者がゴルフ場に求めるもの(例):
- 1. カートのフェアウェイ乗り入れ許可の拡大:
歩行負担の軽減は非常に重要。 - 2. 歩きやすいコース内の動線確保:
急な坂道や段差の解消、手すりの設置など。 - 3. 休憩スペースの充実:
コース内やクラブハウスに、気軽に休める場所を増やす。 - 4. 緊急時対応の整備:
AEDの設置場所の明示、スタッフの救急講習受講など。 - 5. バリアフリー設計の推進:
スロープの設置、手すり付きトイレなど、誰にとっても使いやすい施設へ。 - 6. 予約システムの簡便化:
電話予約だけでなく、シニアにも分かりやすいオンライン予約システム。
これらの課題に対応していくことが、これからのゴルフ場運営にはますます重要になるだろう。
地域と高齢者をつなぐ社交空間としての可能性
ゴルフ場は、単にゴルフをプレーする場所としてだけでなく、地域社会における高齢者の健康増進や孤立防止、交流促進の拠点としての役割も担えるのではないだろうか。
例えば、シニア向けのゴルフ教室や健康セミナーの開催、地域住民が気軽に立ち寄れるカフェスペースの設置などが考えられる。
また、ゴルフを通じて世代間の交流が生まれることも期待できる。
孫と一緒にプレーを楽しむ祖父母の姿は、ゴルフ場にとって最も微笑ましい光景の一つだ。
ゴルフ場が、高齢者にとって生きがいを見つけ、社会とのつながりを維持できるような「社交空間」となること。
それは、これからの超高齢社会において、非常に大きな価値を持つと私は信じている。
まとめ
「あのゴルフ場」に通い続ける理由。
それは、美しい風景や挑戦しがいのあるコースレイアウトだけではない。
そこには、温かい人々との交流があり、積み重ねてきた思い出があり、そして何よりも、自分らしくいられる「居場所」としての価値があるからだ。
常連としての視点は、ゴルフ場の新たな魅力を私たちに教えてくれる。
それは、初めて訪れただけでは気づかないような、細やかな配慮や、変わらぬ日常の安心感だ。
そして、その魅力は、プレーヤー自身の人生と深く結びつき、かけがえのないものとなっていく。
私、佐々木徹は、これからも一人のゴルファーとして、そして一人の紀行作家として、ゴルフコースを歩き、人々と語らい、その記憶を記録し続けていきたい。
そこにはきっと、まだ見ぬ風景と、心揺さぶる物語が待っているはずだから。
読者の皆さまも、ご自身の「第二のふるさと」と呼べるようなゴルフ場との出会いを、大切に育んでいただければ幸いである。
最終更新日 2025年5月8日 by citations